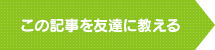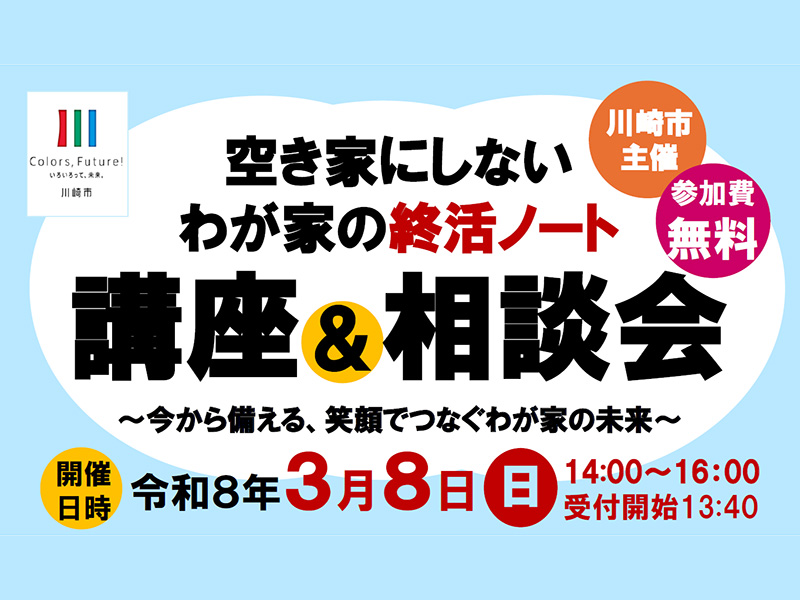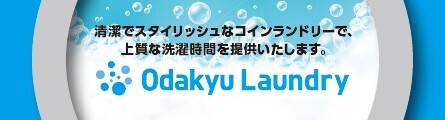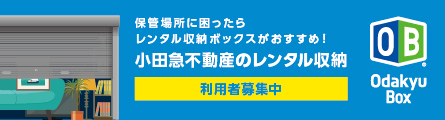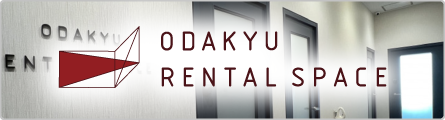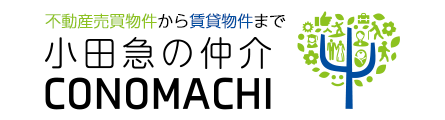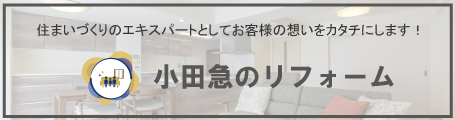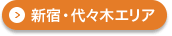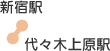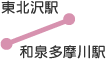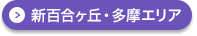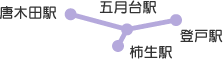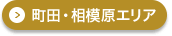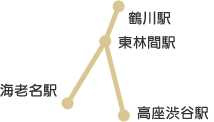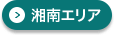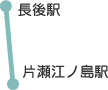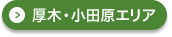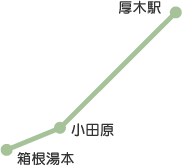拝殿の彫刻や左官職人による鏝絵(こてえ)が見事な「登戸稲荷社」
登戸稲荷社は、登戸駅から徒歩10分ほどの場所にある稲荷神社で、地元の人々に長く親しまれている由緒ある神社です。
その起源は古く、戦国時代に武田家の家臣だった吉沢兵庫がこの地で帰農した際に、邸内鎮守として祀ったことに始まるといわれています。以降、登戸村小名東耕地の鎮守として信仰されてきました。安土桃山時代の天正18年に多摩川の洪水によって社殿が流失するも、中村の旧屋敷敷地を譲り受けて再建。江戸時代後期には嵐による損傷で社殿が修復されるなど、幾度も再建と修復を重ね、現在の社殿は嘉永六年(1853)に再建されたものとなっています。当初の社殿は茅葺だったため、十数年ごとに葺替えられていましたが、昭和28年に瓦葺に。主祭神は宇賀魂大神で、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全などのご利益があるとされています。また、境内には保存樹林として指定された古木が多く、美しい自然の中で参拝ができることも魅力のひとつです。
登戸稲荷社の社殿は、江戸時代の建築技術と美術の融合を示す貴重な文化財です。特に本殿覆屋の漆喰壁に描かれた「鏝絵(こてえ)」は、江戸時代の左官職人による技術の粋を集めた作品として評価されています。鏝絵は漆喰を使用した立体的なレリーフで、稲荷社の本殿には龍や狐などが描かれています。関東大震災で被害を受けたものの、現在も東西面の鏝絵が残されており、ガラスで保護されています。また拝殿の彫刻も見逃せません。迫力ある龍が木鼻に巻き付いており、扉には獅子の透かし彫が施されています。さらに拝殿側面には三国志の武将・高覧が彫刻されており、脇障子には八岐大蛇退治の神話や猿の姿も描かれています。これら彫刻の繊細さやストーリー性は、日本の伝統的職人技術の高さを物語っています。登戸稲荷社は地域の左官職人文化を現代に伝える貴重な存在と言えるでしょう。
普段はひっそりと静かな雰囲気の登戸稲荷社ですが、毎年正月三が日には特別な御朱印が授与され、初詣の参拝者で大変な賑わいを見せます。この御朱印は干支にちなんだデザインが特徴で、その年の印が押される限定的なものであるため、コレクターにも人気です。また参道では焚き上げが行われるなど、正月らしい風情を感じられるイベントも多数行われます。初詣以外にも、2月には祈年祭や節分祭、7月の第1日曜には夏季大祭、9月の第1日曜には例祭、11月23日には新嘗祭が催されており、多くの人でにぎわいます。季節による木々の変化も楽しみながら、彫刻や鏝絵を眺めて歴史に思いを馳せるのもいいのではないでしょうか。
登戸稲荷社
https://www.kanagawa-jinja.or.jp/shrine/1201073-000/
川崎市多摩区登戸2297 044-911-8051この記事は読者リポーターの投稿によるもののため、情報の正確性は保証されません。ご確認のうえご利用お願い致します。